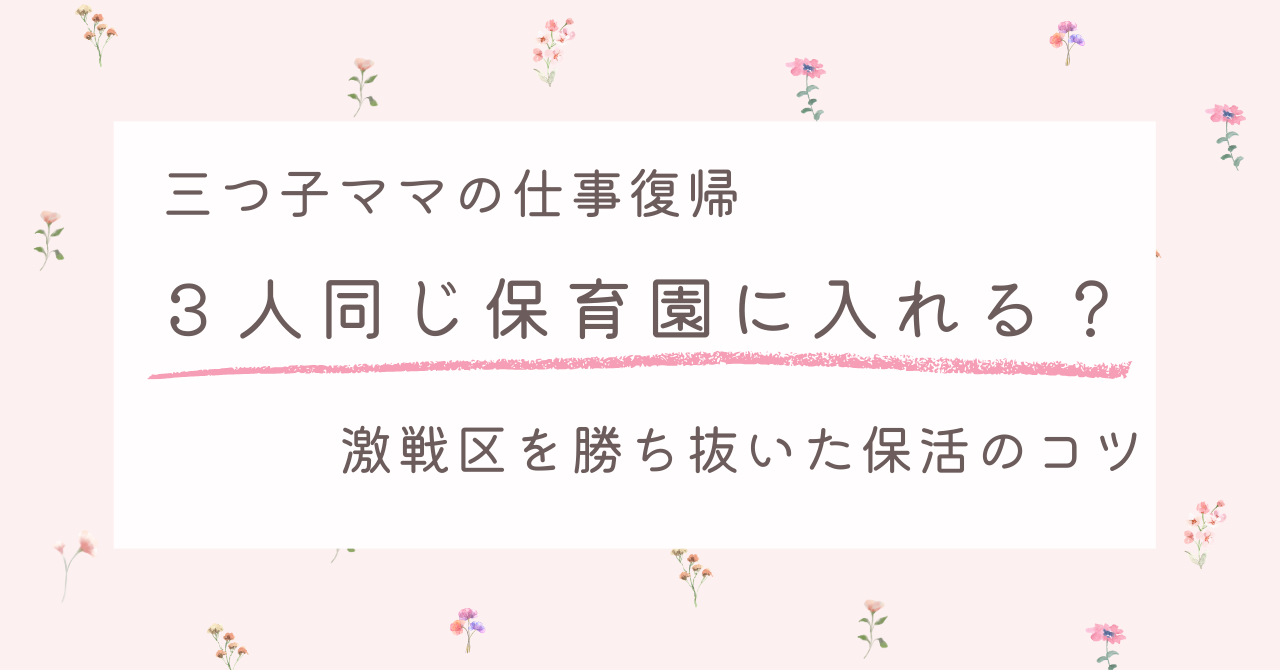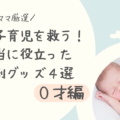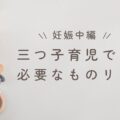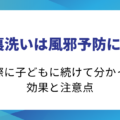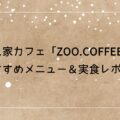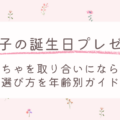「育休明け、三つ子を同じ保育園に預けて仕事復帰したい!」 そう願う多胎児ママにとって、最大の壁となるのが「保活(ほかつ)」です。
1人でも大変な保育園探し。ましてや3人同時に、しかも同じ園に入るなんて無理…と諦めていませんか?
実は、激戦区であっても戦略的な「保活」を行えば、三つ子揃っての入園は決して不可能ではありません。今回は、私が実際に激戦区で三つ子を同じ保育園に入れるために実践した、「勝てる保活のコツ」を余すことなくお伝えします!
目次
1. 三つ子の保活、現実は甘くない?直面する3つの壁
まず知っておきたいのは、多胎児の保活には特有の難しさがあるということです。
- 空き枠の問題: 1人の枠はあっても、同じ年齢(同じクラス)に3人の空きが出ることは稀です。
- 点数の壁: 激戦区では「共働きフルタイム」は当たり前。プラスアルファの加点が必要です。
- 物理的な限界: 3人別々の園になった場合、送迎だけで1日が終わってしまいます。
これらを突破するためには、「情報戦」と「自治体への働きかけ」が鍵となります。
2. 激戦区を勝ち抜く!三つ子ママのための保活戦略5選
私が三つ子全員を同じ園に入れるために行った、具体的なコツを紹介します。
① 「多胎児加点」がある自治体か徹底調査
自治体によっては、多胎児(双子・三つ子)に対して優先入所の加点を設けている場合があります。募集要項の隅々までチェックし、少しでも有利になるポイントを探しましょう。
② 市役所(区役所)の窓口へ何度も足を運ぶ
電話だけで済ませず、直接窓口へ行き、担当者に顔を覚えてもらう勢いで相談しましょう。「3人バラバラになったら物理的に仕事復帰が不可能であること」を必死に伝えることで、調整の際に考慮してもらえるケースがあります。
③ 「第1希望」の書き方に注意
三つ子の場合、「3人一緒なら入園する」のか「バラバラでも良いからどこかに入れたい」のか、希望の出し方が重要です。
- 裏ワザ: 「3人同時入園が必須」と伝えると、3枠空いたタイミングで優先的に案内されることがありますが、その分ハードルも上がります。まずは全園の見学に行き、可能性を探りましょう。
④ 新設園・マンモス園を狙う
枠が少ない小規模園よりも、定員の多い大型園や新設園の方が、一度に複数人の空きが出る確率が高いです。特に4月入園の新設園は、全員が横一線のスタートなので大チャンスです。
⑤ 認可外・一時預かりも「実績」として活用
認可保育園に入る前に、認可外保育園や一時預かりを継続的に利用していると、「受託実績」として加点される自治体が多いです。初期費用はかかりますが、確実に認可を勝ち取るための投資と割り切るのも一つの手です。
3. 三つ子ママの仕事復帰、入園後の準備も忘れずに
無事に保育園が決まったら、次は怒涛の仕事復帰が待っています。
- 送迎シミュレーション: 3人乗せ自転車か、大型ベビーカーか。雨の日はどうするか。
- 病児保育の登録: 1人が熱を出せば、高確率で3人にうつります。病児保育やベビーシッターの登録は必須です。
- 夫との役割分担: 「保活」の段階から、送り迎えや呼び出し対応のルールを決めておきましょう。
諦めないで!三つ子揃っての保育園生活は叶えられる
三つ子の保活は、まさに「戦略」です。 激戦区であっても、早めの情報収集と熱意ある交渉で、道は開けます。
三つ子ママの仕事復帰を、心から応援しています!
👇保育園が決まったらこちらの記事も参考にしてください🌹